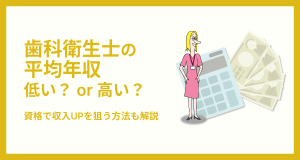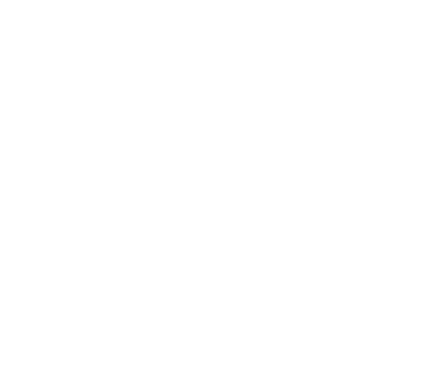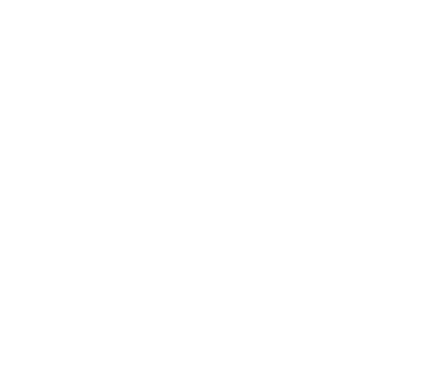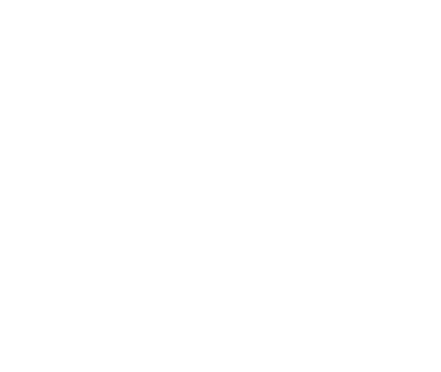歯科衛生士の退職金を徹底解説!制度や相場、控除のポイントまで

歯科衛生士の退職金制度は、歯科医院ごとに制度の有無や金額に差があり、長期的な視点での判断が求められます。一般的な相場はあるものの、支給額は給料体系や勤務年数によっても変動するため、制度の詳細を確認することが重要です。
本記事では、歯科衛生士における退職金の支給有無やその額、算出方法が勤務先や雇用形態にどのように影響するのかを詳しく解説します。
また、就職や転職の際に退職金制度をどのように考慮すべきか、さらには税金に関する基本的な知識など、歯科衛生士としてキャリアを継続していくうえで役立つ情報を幅広くご紹介します。
歯科衛生士の退職金制度の実態

まずは、歯科衛生士の退職金制度について、勤務形態や勤務先によって実態がどのように異なるのかを解説します。
常勤歯科衛生士の74.7%が退職金制度あり
歯科衛生士の退職金制度は、雇用形態によって大きく異なります。
令和2年 歯科衛生士の勤務実態調査によると、常勤の歯科衛生士の74.7%が退職金制度のある職場に勤務していることが明らかになりました。一方で、非常勤の場合はわずか8.3%と、大きな差があります。
この数値は、歯科衛生士の雇用形態が給料に直結していることを示唆しています。
常勤歯科衛生士として働くことで退職金を受け取れる可能性が高まるため、キャリアの選択肢を考える際には、雇用形態ごとの経済的影響の違いを考慮することが非常に重要です。
退職金制度の有無は歯科医院による
日本の法律では、退職金の支払いは企業や医院の裁量に任されており、法的義務はありません。※これは一般企業でも同様であり、退職金制度の有無や支給基準は就業規則や労働契約によって決まります。
特に歯科医院は個人経営が多いため、退職金制度の導入は医院ごとの判断に委ねられているのが実情です。
大手の医療法人や病院・大学病院などでは退職金制度が整備されている傾向がありますが、小規模な診療所では歯科衛生士の退職金が導入されていないケースも少なくありません。
また、歯科衛生士の退職金の相場は勤務先によって異なり、支給基準や金額に幅があります。そのため、就職や転職の際には、退職金制度の有無や支給条件を確認し、長期的なキャリアプランに合った職場を選ぶことが大切です。
特に長年勤めた場合、退職金の有無が将来的な資産形成に大きく影響します。安定したキャリアを継続するためにも、退職金制度が整っている職場を選ぶことが望ましいでしょう。
▼こちらのコラムも要チェック!
退職金の計算方法

歯科衛生士の退職金は、勤務先の歯科医院や医療法人によって計算方法が異なりますが、多くのケースで給料や勤続年数を基準とした計算方式が採用されています。
代表的な退職一時金の算出方法※としては、以下のような方式が挙げられます。
- 退職金算定基礎額×支給率
- 勤務年数に応じた一定額
- ポイント制(退職金ポイント×ポイント単価)
- 退職金算定基礎額×支給率+一定額
※参考:産業労働局 中小企業の賃金・退職金事情(令和4年度版)
また、退職金の基となる給料水準について、令和2年 歯科衛生士の勤務実態調査によると、常勤歯科衛生士の約8割が年収130万円以上500万円未満の範囲にあり、最も多い層は年収300万円以上400万円未満(35.3%)となっています。
このデータは業界全体の相場を示すものであり、歯科衛生士の退職金額にも一定の影響を与えることがわかります。
▼こちらのコラムも要チェック!
仮に、退職金が「基本給×勤続年数×退職事由係数」によって算出されるとした場合、基本給が28万円で10年間勤務した歯科衛生士が、自己都合退職をした場合の支給率が0.8であるならば、退職金は以下の計算式で求められます。
28万円 × 10年 × 0.8 = 224万円
ただし、退職金の計算方法や算定基準は、歯科医院の経営形態や規模、さらには法人か個人経営かによっても大きく異なるため、注意が必要です。
法人経営の歯科医院では、より整備された退職金制度が設けられていることが多い一方、個人経営の医院では制度が不明確であったり、退職金支給の取り決めが少ない場合もあります。
将来の資産形成や安定したキャリアの継続を見据え、自身の勤務先における退職金制度の有無や算出基準を事前に確認しておくことが重要でしょう。
歯科衛生士の退職金相場と税金の基礎知識

退職金の額は勤務先の規模や経営方針に左右されますが、医療業界全体の目安をもとに、相場を把握することが重要です。歯科衛生士の退職金相場や税金について、基本的なデータを解説します。
退職金の相場
歯科衛生士の退職金は、勤務先の歯科医院の規模や経営方針によって大きく異なりますが、一般的な医療業界の相場を基準にすると、一定の傾向が見えてきます。
産業労働局 中小企業の賃金・退職金事情(令和4年度版)のモデル退職金によると、医療・福祉業界で定年まで勤めて退職する場合に受け取れる金額の目安は以下の通りです。
- 高卒者の場合: 約332万3,000円
- 大卒者の場合: 約342万4,000円
この金額は、病院や介護施設を含む医療業界全体の平均値であり、歯科医院単独の場合は、規模や経営形態によってさらに低くなることも考えられます。
特に小規模な個人経営の歯科医院では、退職金制度自体が存在しない場合も少なくはなく、そのため、実際の支給額はこの目安の金額と異なることがあります。
したがって、退職金の受け取りに関しては、勤務先の状況を十分に確認したうえで、あくまで一つの参考値として捉えることが賢明でしょう。
退職金でかかる税金について
退職金は、長年の勤続に対する報奨として支給されるため、税制面で優遇されています。原則として、退職所得は他の所得と分離して課税され、退職所得控除が適用されるため、税負担が軽減されます。※
退職金の支払い時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで、源泉徴収のみで課税関係が終了し、確定申告は不要となります。
ただし、申告書を提出しない場合は、一律20.42%の所得税等が源泉徴収されるため、確定申告による精算が必要です。
※参照:国税庁 退職金と税
退職金の支給タイミングについて

歯科衛生士が退職金を受け取るためには、一般的に3年以上の勤続年数が必要となる場合が多いです。
この要件は、退職金制度を導入している企業において、退職一時金を支給するための最低勤続年数として、3年という基準が最も高い割合を占めるという調査結果※に基づいています。
自己都合退職、会社都合退職にかかわらず、この傾向に大きな違いは見られません。
ただし、3年という勤続年数はあくまで一般的な指標に過ぎません。実際の退職金支給条件は、勤務先の就業規則や労働契約に基づいて定められており、個々の歯科医院や法人ごとに異なる場合が多いです。
歯科衛生士の退職金の相場は、給料水準や退職金制度の有無により異なるため、勤務先の具体的な条件や支給時期については、就業規則や労働契約書を十分に確認し、疑問点があれば院長などに問い合わせることをお勧めします。
※参照:産業労働局 中小企業の賃金・退職金事情(令和4年度版)
まとめ
歯科衛生士の退職金制度は、キャリア形成において極めて重要な要素であり、その内容は歯科医院の経営方針や規模によって大きく異なります。
一般的に、歯科衛生士の退職金の支給額や算出方法は勤務年数に基づくことが多く、3年以上の勤続が支給の前提となっている医院が多数を占めています。
特に、給料や退職金の関係は従業員の長期的なキャリアにも影響するため、安定した給料とともに、退職金制度を整備することが重要です。
ここでご紹介したいのが、「Apotool & Box for Dentist」です。Apotool & Boxは効率的な予約管理や経営分析機能を駆使し、歯科衛生士をはじめとするスタッフが業務に集中できる環境を提供します。
医院の発展と持続可能な経営を見据え、退職金制度の見直しや改善に取り組むことで、より充実した職場環境を作り上げていきませんか?ご興味のある方は、是非お問い合わせください。
- Apotool & Box サポートセンター
- 平日 10:00~18:00
Tel:03-6403-4880
お問い合わせフォームはこちら