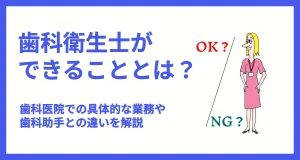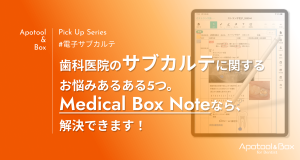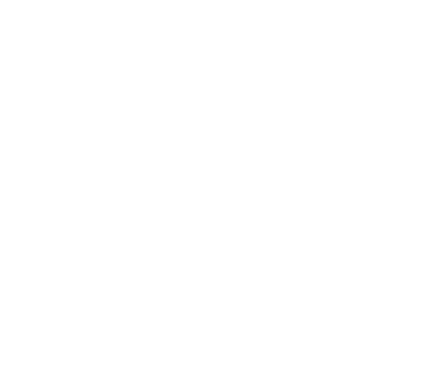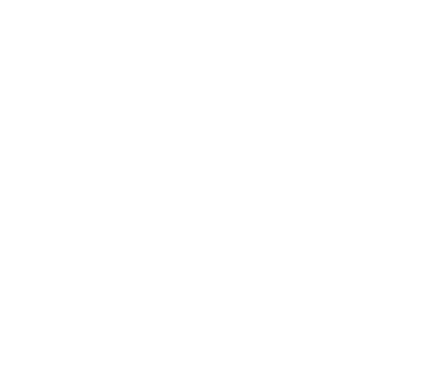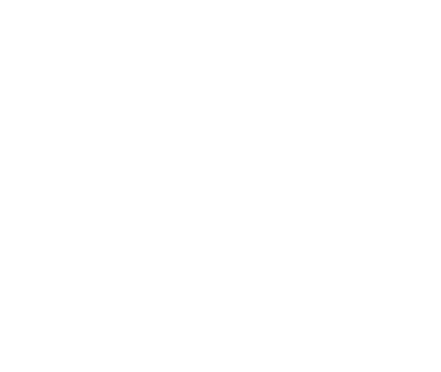歯科衛生士が打てる麻酔とは?業務範囲と必要な知識について解説
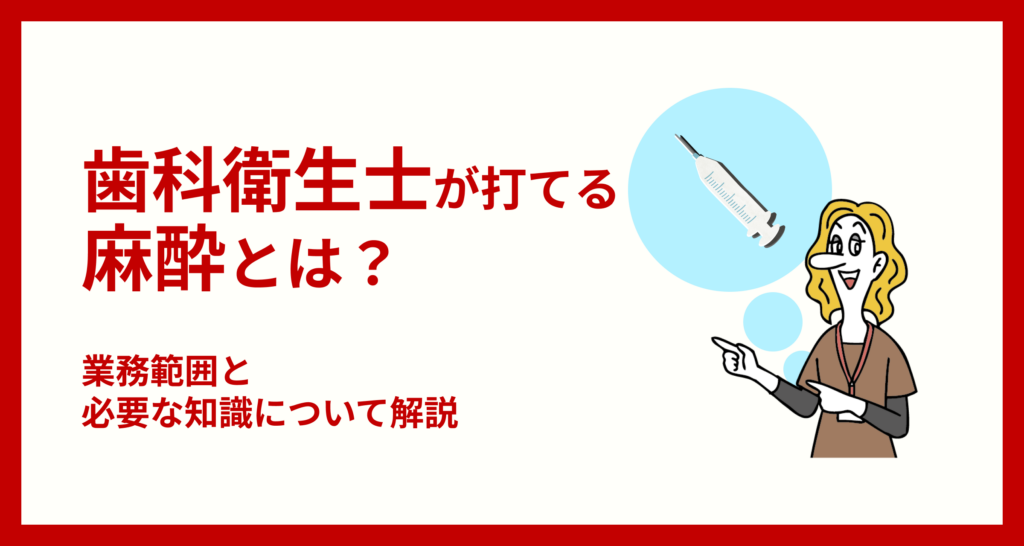
歯科衛生士は歯科医師の指示のもとでさまざまな業務を行いますが、麻酔に関しても特定の範囲で関与することができます。
本記事では、歯科衛生士の業務範囲における麻酔の位置づけや必要な知識、注意点について詳しく解説します。
歯科衛生士は麻酔を打てる?

一般にはあまり知られていませんが、歯科衛生士は歯科医師の指示のもとであれば診療補助として麻酔を行うことが可能です。
法律上、歯石除去などの医療行為と同様に、適切な指示があれば局所麻酔も実施できるとされています。ただし、歯科医師が的確な指示を出せる状況であることが条件となります。
麻酔を打てる治療とそうでない治療がある
歯科衛生士が行える麻酔には業務範囲が定められており、すべての治療で麻酔を行えるわけではありません。
歯科衛生士の業務範囲について、相対的歯科医行為と絶対的歯科医行為に分類して解説します。
相対的歯科医行為はOK
相対的歯科医行為とは、法律上は本来歯科医師のみが行うことができる医療行為であるものの、一定の条件下で歯科衛生士が実施可能とされる行為のことを指します。
相対的歯科医行為を歯科衛生士が行うには、以下の条件を満たす必要があります。
・歯科医師の指示のもとで行うこと
・歯科医師の監督下で行うこと
・歯科衛生士が適切な知識・技術を習得していること
麻酔に関しては、以下の2種類が相対的歯科医行為に該当します。
表面麻酔
表面麻酔とは、歯科治療の際に針を使わずに歯肉や口腔粘膜の表面に麻酔薬を塗布し、感覚を麻痺させる方法です。
これは診療補助の一環として、歯科医師の指示のもと歯科衛生士が行える麻酔です。
浸潤麻酔
浸潤麻酔とは、歯の周囲の歯肉や粘膜に麻酔薬を注射し、神経を一時的に麻痺させる方法です。
実は歯科衛生士も、SRP時などに鎮痛を目的として浸潤麻酔を行うことが認められています。ただし、歯科医師の適切な指示と管理のもとで実施される必要があります。
絶対的歯科医行為はNG
絶対的歯科医行為とは、歯科医師のみが行うことを許されている医療行為であり、歯科衛生士を含む他の医療従事者がいかなる条件下でも実施できない行為を指します。
これは、高度な専門知識や技術が必要であり、誤った処置が患者の健康に大きな影響を与える可能性があるためです。例えば、抜歯、歯の切削、外科手術などが含まれます。
麻酔に関しては以下の2種類が絶対的歯科医行為に該当します。
伝達麻酔
伝達麻酔とは、神経の根元に麻酔薬を注射し、その神経が支配する広範囲の感覚を麻痺させる麻酔法です。主に外科的処置を行う際に使用されます。
伝達麻酔は絶対的歯科医行為に分類され、歯科医師のみが実施できる処置です。
全身麻酔・静脈内鎮静
全身麻酔は患者の意識を完全に失わせる麻酔法で、静脈内鎮静は軽く意識をぼんやりさせる方法です。主に親知らずの抜歯、顎の手術、インプラント手術など、大掛かりな処置に使用されます。
これらの麻酔は絶対的歯科医行為に分類され、歯科医師または麻酔専門医のみが実施可能です。
▼こちらのコラムも要チェック!
歯科衛生士に必要な麻酔の知識

歯科衛生士が安全に麻酔の補助を行うためには、麻酔に関する正しい知識と技術を身につけることが重要です。ここでは、歯科衛生士に必要な麻酔の知識について解説します。
歯科関連法令
歯科衛生士が麻酔を行うには、歯科医師の指示のもとで実施することが法律で定められています。 具体的には、歯科衛生士法や医師法・歯科医師法などの法令を理解し、業務範囲を正しく把握することが重要です。
違法な医療行為を防ぐためにも、常に最新の法改正情報を確認する必要があります。
正確な麻酔技術
麻酔を安全に行うためには、注射針の刺入角度や深さ、注入速度などの技術が求められます。 針を正確に刺入し、痛みを最小限に抑えるための技術を習得することが大切です。
また、針の進入時の抵抗感や患者の反応を注意深く観察しながら操作することが求められます。
麻酔薬の種類と作用
歯科で使用される麻酔薬にはリドカインやアーティカインなど、いくつかの種類があります。 それぞれの麻酔薬は作用時間や効果の強さが異なるため、治療内容に応じて適切な麻酔薬を選択することが重要です。
また、血管収縮薬の有無によっても作用が変わるため、その違いを理解する必要があります。
麻酔薬の適正な使用量と最大用量
麻酔薬は、体重や年齢に応じた適正な使用量が決められています。 過剰に投与すると中枢神経系や心血管系に影響を及ぼす危険があるため、最大用量を超えないよう注意が必要です。 特に、小児や高齢者には慎重な投与が求められます。
血管収縮薬の役割と注意点
エピネフリンなどの血管収縮薬は、麻酔薬の持続時間を延ばし、出血を抑える効果があります。 しかし、特定の薬剤との相互作用があるため、患者の服用中の薬の確認も重要です。特に、高血圧や心疾患などの持病がある方には慎重に使用する必要があります。
麻酔の禁忌と副作用
麻酔薬には使用が制限されるケースがあるため、患者の体質や病歴に応じた判断が求められます。 また、副作用として局所の腫れやアレルギー反応、血圧の変動などが起こることがあります。
これらを事前に把握し、適切な対策を講じることが大切です。
合併症・副作用の認識と対応
麻酔後には、神経損傷や血腫、持続的な痺れなどの合併症が起こることがあります。 また、誤って血管内に注入してしまうと、めまいや動悸などといった全身的な副作用が現れる可能性があります。
これらの症状が発生した場合に、速やかに対処できる体制を整えておくことが求められます。
患者の既往歴・アレルギーの確認
麻酔を安全に行うためには、患者の既往歴やアレルギーの有無を事前に確認することが不可欠です。 特に、麻酔薬やラテックスにアレルギーを持つ患者には代替手段を考慮する必要があります。 また、妊娠中や基礎疾患のある患者への配慮も重要です。
緊急時の対応
万が一、アナフィラキシーショックや麻酔中毒などの緊急事態が発生した場合、迅速な対応が求められます。 酸素投与や救急連絡の流れを理解し、必要に応じて救急蘇生のスキルを身につけることが重要です。
また、緊急時に備えて、救急薬剤や器具の管理も徹底する必要があります。
麻酔の痛みを抑えるポイント

歯科治療で行う麻酔は治療中の痛みを軽減するために行いますが、麻酔自体の痛みが苦手な方も少なくありません。 ここでは、痛みを抑えるためのポイントを紹介します。
極細の注射針を使用する
麻酔の痛みの原因の一つは、針を刺すときの痛みです。一般的に、針が太いほど刺したときの痛みを感じやすくなります。そのため、極細の注射針を使用することで痛みを大幅に軽減できる可能性が高まります。 現在では、35Gなどの非常に細い針が使用されることもあり、針を刺す際の刺激が少なくなっています。
注入速度に注意する
麻酔時の痛みは針を刺す痛みだけでなく、麻酔薬を注入するときの圧力も影響します。一気に麻酔薬を注入すると、組織が急に膨らみ強い痛みを感じる原因になるため、ゆっくりと時間をかけて注入することで痛みを和らげることができます。 最近は、電動麻酔注射器を使用して一定の速度で麻酔薬を注入することで、痛みを軽減する方法も普及しています。
麻酔薬の温度を調整する
麻酔薬の温度も痛みに影響を与える要因の一つです。冷たい麻酔薬を注入すると刺激を感じやすくなるため、体温に近い約37℃に温めることで痛みを緩和できます。さらに、シリンジウォーマーなどを用いた温度管理により、患者の負担を軽減することが可能です。
歯科衛生士が麻酔を行うときの注意点

歯科衛生士が麻酔を行う際に注意すべきポイントについて解説します。
正しい麻酔の手技とポイントを学ぶ
麻酔を安全に行うためには、正しい技術や適切な薬剤の使用方法を学ぶことが重要です。 そのためには専門のセミナーや講習会に参加し、最新の知識や技術を身につけるとよいでしょう。
また、模型を用いた実習などを通じて経験を積むことで、より確実な施術ができるようになります。
知識と経験を得るまでは必ず補助をつける
麻酔の施術は、初めのうちは歯科医師や経験のある歯科衛生士のサポートを受けながら行うことが大切です。 自信を持って実施できるようになるまでは、常に補助者とともに確認しながら進めましょう。
そうすることで、技術の向上だけでなく万が一のトラブルにも迅速に対応することができます。
患者への説明とコミュニケーションを大切にする
歯科衛生士が麻酔を行うことはあまり周知されていないため、患者に対して事前に十分な説明を行い、不安を和らげることが重要です。 麻酔の目的や安全性を丁寧に伝え、納得してもらうことで安心感を持ってもらえます。
また、痛みや違和感がある場合にはすぐに伝えてもらえるよう話しやすい雰囲気を作ることも大切です。
歯科衛生士の麻酔に関する資格

歯科衛生士は、特定の研修や試験を受けることで、麻酔に関する専門的な認定資格を取得することができます。その代表的なものが以下の2つです。
日本歯科麻酔学会認定歯科衛生士
日本歯科麻酔学会認定歯科衛生士は、歯科麻酔に関する高度な知識と技術を有する歯科衛生士を認定する資格です。
取得には全身麻酔や静脈内鎮静法を行う施設での実務経験や、学会発表・論文執筆が求められます。また、資格取得後も定期的な更新が必要です。
この資格を持つ歯科衛生士は、麻酔管理の補助や患者のバイタルサインの管理、安全対策の実施などを担当し、歯科治療の安全性向上に貢献します。
臨床歯科麻酔認定歯科衛生士
臨床歯科麻酔認定歯科衛生士は、局所麻酔や静脈内鎮静法の補助に関する専門的な知識と技術を認定する資格です。取得するには学会が指定する研修を受講し、試験に合格することが必要です。
この資格を取得した歯科衛生士は、歯科医師の指示のもとで浸潤麻酔の補助や実施、静脈内鎮静法時のモニタリング補助、救急対応などを行います。この資格を持つことで歯科衛生士としての専門性を高め、キャリアの幅を広げることができます。
まとめ
歯科衛生士が行える麻酔には、表面麻酔と歯科医師の指示のもとで行う浸潤麻酔の2種類があります。
安全な麻酔の実施には法令の理解、正確な手技、麻酔薬の適正使用、副作用や禁忌の把握が求められます。さらに、患者の既往歴やアレルギーの確認、緊急時の対応スキルを身につけ、歯科医師と連携しながら患者の安全を守ることが重要です。
患者情報の共有には、Apotool & Box for Dentistのデジタルサブカルテ「Medical Box Note」が非常に有効です。
Medical Box Noteを活用することで、サブカルテをクラウド上で管理できるようになります。複数の端末から同時に情報を閲覧できるため、治療にあたる歯科医師や歯科衛生士が複数名で患者情報を共有・確認することが可能です。
この機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか。
▼関連コラムはこちら
- Apotool & Box サポートセンター
- 平日 10:00~18:00
Tel:03-6403-4880
お問い合わせフォームはこちら